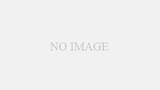「ピチカート」とはバイオリンやチェロなど弦楽器の演奏方法の1つで、弦を指ではじいて音を出す演奏方法を言います。
弦楽器は通常、弓で弦をこすり音を出していますが、指ではじくことでポンッと軽やかな音を出すことが出来ます。
今回はそんな「ピチカート」の演奏が印象的なクラシック曲を紹介していきます。
ピチカートとは
ピチカート(pizzicato)とは、イタリア語で「つまむ」「はじく」という意味。弦楽器(ヴァイオリンやギター、ハープなど)で、通常は弓(アルコ:arco)で弾くところを、右手または左手の指で直接弦をはじいて音を出す技法です。
楽譜には「pizz」と書かれており、再び弓で弾く場合は「arco」と表記されます。また、通常右手で行うピチカートですが、左手で行う場合は「+」と表記されます。
楽譜に初めて登場したのは1607年にクラウディオ・モンテヴェルディが作曲したオペラ《オルフェオ》第3幕。チェンバロや弦楽器の楽譜に「pizzicato」と記されており、これが現存する最古のピチカート記譜とされています。
即興や口伝などでピチカート奏法はされていたかも知れませんが、楽譜として残っている最古のピチカートは《オルフェオ》です。
では次に、ピチカートを用いた曲を何曲か紹介します。
ラヴェル:弦楽四重奏曲より第2楽章
ラヴェルはフランスの作曲家です。 この作品は全4楽章で演奏時間は約30分、ピチカートが出てくるのは第2楽章です。
悲しみを感じさせるバイオリンのメロディーと激しいピチカートの音色が対照的で素晴らしいです。
バルトーク:弦楽器と打楽器とチェレスタのための音楽
バルトーク(1881〜1945年)はハンガリーの作曲家です。バルトークはピチカートを多く使う作曲家で、この作品でも上手に活用しています。
通常のピチカートは横に弾いて音を出すのに対して、バルトークのピチカートは指板(弦を押さえる時に触れる板)と垂直に弾くため、弾かれた弦が指板にあたり「バチン!」と音がする奏法を好んで使っており、「バルトークピチカート」と呼ばれています。
ドリーブ:「シルビア」より「ピチカート」
ドリーブ(1836~1891年)は、フランスの作曲家です。
「シルビア」はバレエ音楽で、第3幕にこの曲が流れます。軽快でスピーディーなピチカートの響きと、ゆったりとしたフルートの音色が対照的で可愛らしい曲です。
ヨハン・シュトラウス2世:ピチカートポルカ
ヨハン・シュトラウス2世(1825~1899年)は、オーストリア出身の作曲家です。
「美しく青きドナウ」や「皇帝円舞曲」、「こうもり」序曲などワルツやポルカ、オペラなど数多くの親しみやすい曲を多く作っています。
こちらの曲は最初から最後までピチカートなので弓は持たずに演奏します。ちなみに、弓を使わない時は太ももに乗せておきます。
ルロイアンダーソン:Plink Plank Plunk
ルロイアンダーソン(1908〜1975年)はアメリカの作曲家です。本物のライプライターを使った曲や、演奏中にタンゴを踊る曲、時計の音を表現した曲などユーモアがありとても耳馴染みやすい曲を多く作っています。
「Plink Plank Plunk」は終始ピチカート演奏の曲なので、弓を持たずに演奏します。また、曲調が明るく楽しい曲なので、アンコールでちょっとふざけて演奏したりされ人気の楽曲です。
「plink」と「plunk」には、「ポロンと鳴らす」という意味があります。「plank」にそう言った意味はなく「厚板」という意味があります。楽器をこすって「キュッ」という音を出すので、この音の出し方と語呂の良さで選ばれたのかも知れません。
どことなく、ドラゴンクエストⅡのパスワード入力画面で流れる曲「Love song 探して」に聴こえるのは年齢のせいでしょうか(笑)
チャイコフスキー:交響曲第4番第3楽章
チャイコフスキー(1840〜1893年)はロシアの作曲家です。交響曲は6つ作曲し、4番目の交響曲にピチカートを使った楽章があります。
3楽章は、弦楽器、木管楽器、金管と打楽器と3部に分かれて曲が進んでいきます。この楽章は交響曲では珍しくずっとピチカートです。
交響曲第4番自体は重々しく、金管楽器が大活躍する曲ですが、3楽章は一転して軽やかな曲調が人気の曲です。
パガニーニ:24のカプリースより24番
イタリアの作曲家でありヴァイオリニストであるパガニーニが作曲した、ヴァイオリンの難曲としてとても有名な作品です。「カプリース」とは奇想曲のことで、型にとらわれない自由な形式で24曲作られました。そして今回ご紹介するのが最後の作品24番です。
変奏曲スタイルで作られた本作はヴァイオリン独奏曲ではありますが、1人で演奏しているとは思えない超絶技巧の連続で、3度、6度、オクターブ、10度の重音、トレモロにスタッカート、超高音に移弦の激しい曲などなど、ヴァイオリンの難しいテクニックをこれでもかと詰め込んだ信じられない鬼畜な作品です。
パガニーニ自身がヴァイオリンの名手で、あまりのテクニックに「悪魔に魂を売って手に入れた」と言われるほどの腕前だったのはとても有名な話です。
その中で登場するのが、第9変奏曲の左手でのピチカートです。通常ピチカートは右手で行いますが、右手はスタッカートで弦を弾きながら、左手の弦を押さえていない指でピチカートを行います。
見ていてもどう演奏しているのか全く理解できませんが、とにかく異常な事をしていることが分かるので、動画をご覧ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
ピチカートは弾む軽やかな音色で明るい雰囲気を出したり、激しい場面でも用いられる特徴的な技法でとても印象に残ります。今回紹介した曲以外にもピチカートはたくさんの楽曲で使用されているので、随時更新していきます。