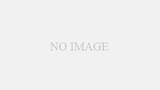クラシック音楽の歴史には「もしこの作品が完成していたら」と語り継がれる未完の名曲がいくつも存在します。中でもロシアの作曲家アレクサンドル・ボロディンの交響曲第3番は、その異色の作曲家人生とともに、今なお多くの人々の心を惹きつけてやみません。今回はこの作品が生まれた背景や、未完に終わった経緯、そして残された楽章の魅力を、初心者の方にもわかりやすく丁寧に解説します。
アレクサンドル・ボロディンという人物
異色の作曲家、化学者ボロディン
ボロディン(1833-1887)は、一言でいえば**「本職が化学者の作曲家」**。ロシア帝国の首都サンクトペテルブルクで生まれ、幼少期から音楽と科学の両方に魅了されて育ちました。裕福な家庭に生まれ、ピアノやチェロを嗜む一方、化学の道にも早くから才能を発揮し、大学では医師免許と化学の学位を取得。その後、有機化学の分野でいくつもの功績を挙げ、教鞭を執るようになりました。
驚くべきことに、ボロディンは作曲をほぼ独学で学び、空いた時間に趣味として交響曲や室内楽、オペラを作り上げていったのです。この特異な経歴は、クラシック音楽史の中でも極めて稀な例といえます。
ロシア五人組の一員として
19世紀後半、ロシアの音楽界ではロシア民族の独自性を音楽で表現しようとする運動が盛り上がっていました。これが「ロシア五人組(キュイ、バラキレフ、ムソルグスキー、リムスキー=コルサコフ、ボロディン)」の活動です。
ボロディンはその一員として、民謡を素材にした旋律や東洋風の音階を取り入れるなど、ロシア独自の音楽言語を追求し、自身の作品にも反映させていきます。
音楽活動と社会活動
また、ボロディンは単なる音楽家・科学者ではなく、社会活動家としても知られていました。特に女性の教育機会拡充に尽力し、ロシア帝国初の女子医学校設立にも深く関わりました。忙しい日常の中、音楽はまさに心の拠り所であり、喜びの源泉だったのです。
交響曲第3番の誕生と背景
作曲のきっかけと制作の経緯
ボロディンが交響曲第3番の作曲を始めたのは1886年ごろ。前年にオペラ《イーゴリ公》の作業も一段落し、再び交響曲の構想を練り始めました。
彼の頭の中には既に「ロシア民謡のリズムを生かした力強く、躍動感のある交響曲」のイメージがありました。しかし、化学者としての公務、講義、研究、女子医学校の設立活動といった多忙な日常の中で、作曲に割ける時間はわずか。
それでも、ボロディンは夜遅くや休日を使って少しずつ交響曲第3番の構想を進め、第1楽章と第2楽章のスケッチを完成させます。ところが、その矢先の1887年2月27日、ボロディンは友人宅の舞踏会の最中に倒れ、心臓発作で急逝。享年53歳。
交響曲第3番はわずか2つの楽章の草稿のみを残し、未完のままとなってしまったのです。
グラズノフによる補筆と管弦楽化
ボロディンの死後、親友で弟子でもあったアレクサンドル・グラズノフが、この交響曲のスケッチを発見。彼は敬意を込めて、残された断片をもとに管弦楽用に編曲し、2つの楽章による組曲形式としてまとめあげました。
重要なのは、未完成部分を無理に補作するのではなく、ボロディンの残した部分のみを尊重してまとめた点。これによって今日、私たちはこの幻の交響曲第3番を、未完ながらも完成度の高い小交響曲のような作品として楽しむことができるのです。
交響曲第3番 各楽章の詳しい解説
第1楽章:アレグレット(Moderato)
交響曲第3番は、軽やかで親しみやすい冒頭から始まります。ボロディン独特のロシア民族音楽の旋律が柔らかく流れ、どこか懐かしさと郷愁を誘う響き。中でも、リズムの揺らぎと旋律の滑らかさが特徴で、民謡のような親しみやすさを感じさせます。
管弦楽の使い方も非常に巧みで、弦楽器のふくよかな響きと木管楽器の軽やかな掛け合いが絶妙。クラリネットやフルートの旋律が印象的に浮かび上がり、まるで緑の草原に吹く風のような爽やかさを表現しています。
中間部では短調に転じ、やや陰りのある旋律が登場。この明暗のコントラストが非常に美しく、ボロディン特有のロマンティックな情感を漂わせます。そして再び冒頭の旋律に戻り、穏やかに楽章を閉じます。
第2楽章:スケルツォ(Vivace)
第2楽章は、跳ねるようなリズムと躍動感あふれる旋律が魅力のスケルツォ。スケルツォとはイタリア語で「冗談」「戯れ」を意味し、その名の通り、軽快で生き生きとした性格の楽章です。
冒頭から活発な弦楽器の刻みと、管楽器の軽妙なフレーズが絡み合い、ロシアの民族舞踊を思わせるリズムが展開されます。特に3拍子のリズムにアクセントが加えられ、独特の躍動感が生まれています。
中間部は一転して、夢見るような穏やかな旋律が現れ、弦楽器の柔らかな響きに木管楽器が寄り添うように展開。この対比が実に見事で、ボロディンの詩的な感性が垣間見える瞬間です。
やがて冒頭の活発な主題が戻り、華やかに楽章を閉じます。この第2楽章は、ボロディンの持ち味である軽妙さと民族色、詩情を併せ持つ傑作といえるでしょう。
未完ゆえの魅力
交響曲第3番は、未完のまま残されたからこそ「完成していたらどんな名作になっていたか」という想像を掻き立てます。クラシック音楽には「未完成作品ならではの美しさ」があり、シューベルトの《未完成交響曲》やブルックナーの第9番など、未完のまま残されたことで特別な存在感を放つ作品も少なくありません。
ボロディンの第3番もその一つ。完成していたら、さらに民族色豊かな楽章が続き、堂々たるフィナーレを迎えていたことでしょう。その「もしも」を想像しながら聴くのも、この作品の楽しみ方のひとつです。
おわりに
アレクサンドル・ボロディンの交響曲第3番は、化学者という異色の経歴を持ちながら、ロシアの民族色と詩的感性を織り交ぜた音楽を遺した彼の音楽人生の集大成とも言える作品です。未完であることがかえって神秘性とロマンを与え、現代でも多くの人々に愛されています。
ぜひ一度、ボロディンの交響曲第3番を聴いてみてください。19世紀ロシアの風景と、未完の美学があなたの心にそっと寄り添ってくるはずです。