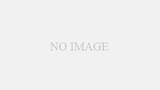冬の静かな夜、窓の外にはしんしんと雪が降り積もり、遠くで風が木々を揺らす。そんな情景が音楽になったとしたら、きっとこんな響きになるはず。今回ご紹介するのは、チャイコフスキーの《交響曲第1番「冬の日の幻想」》。彼の交響曲の中では比較的知られていない存在ですが、実は詩的で親しみやすく、ロマンティックな魅力にあふれた作品です。
チャイコフスキーといえば《白鳥の湖》《くるみ割り人形》《交響曲第6番「悲愴」》などが有名ですが、その原点ともいえるこの交響曲には、若き作曲家の瑞々しい感性と、交響曲という形式に挑んだ情熱が詰まっています。今回は、その魅力をじっくり掘り下げ、曲の背景や聴きどころを紹介していきます。
チャイコフスキーとは
ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー(1840年~1893年)はロシアの作曲家です。バレエ音楽「白鳥の湖」、「くるみ割り人形」、交響曲第6番「悲愴」、弦楽四重奏曲第1番、序曲「1812年」、バイオリン協奏曲、弦楽セレナーデ、スラブ行進曲などなど、ざっと挙げてもまだ足りないくらい有名な作品を多く残した大作曲家です。
いまではベートーヴェンやモーツァルトなどと肩を並べる有名な作曲家ですが、本作を書いていた頃はまだ20代半ば。モスクワ音楽院の教員としての職を得たばかりで、作曲家としてもまだ駆け出しの存在でした。
作曲時の背景/現在の評価
そんなチャイコフスキーの最初の交響曲はどのようにして誕生したのでしょうか。作曲時の背景、状況から現在の評価までを簡単にご紹介します。
「ロシア五人組」と西洋音楽
1866年、チャイコフスキーは寄宿先のニコライ・ルビンシテインのすすめにより、交響曲の作曲を始めました。当時、ロシアでは交響曲というジャンルはまだ発展途上であり、また、ムソルグスキー、ボロディン、リムスキー=コルサコフといった民族主義音楽家集団「ロシア五人組」が活躍しており、ロシアの民族音楽を重視する風潮が高まっていた時でした。
そんな中、アカデミックな西洋音楽教育を受けたチャイコフスキーは、自らの音楽的立ち位置に悩んでおり、五人組のような民族色を強調するべきか、それとも西洋的な形式美を重視するべきか。作曲は難航し、精神的にも追い詰められ、健康を崩すほどでした。
特に形式の扱いに苦労し、スコアを完成させるまでには何度も挫折を繰り返したと言われています。この交響曲第1番は、まさにそうした彼の葛藤の中から生まれた作品といえます。
初演での酷評、3度の改訂
1868年にモスクワで初演されたが、当時の評価は決して芳しいものではありませんでした。チャイコフスキー自身もこの作品に不満を抱えており、2度の改訂が重ねられることになります。晩年になってもこの作品をあまり演奏会で取り上げることがなく、自らの代表作とは考えていなかった節があるようでした。
しかし、こうして様々な苦悩を乗り越え作曲された《交響曲第1番「冬の日の幻想」》の素晴らしい点は、とにかく冬の情景描写が美しいところです。まだ20代半ばだったチャイコフスキーの繊細な感性と、ロマン派ならではの詩情豊かな音楽が全編に漂っています。
また、1楽章、2楽章にもチャイコフスキー自身が付けた副題がありますが、特に第2楽章《陰気な土地、霧の土地》は、静寂な雪景色の中を旅する情景が目に浮かぶような詩的な音楽で、この作品の最大のハイライトといえます。
現在の評価
20世紀以降になると、この交響曲はチャイコフスキーの若き日の瑞々しい感性と詩情を味わえる貴重な作品として再評価されるようになり、近年では冬の季節になると取り上げられる機会も増えており、クラシック・ファンの間でも隠れた名作として親しまれています。
また、この作品には2楽章以外にもチャイコフスキーらしいメロディのセンスを随所に感じられ、彼の交響曲第4番以降にみられる重厚なドラマティシズムとは違い、軽やかで透明感のある響きが心地よく、クラシック初心者でも親しみやすい作品になっています。
チャイコフスキーの交響曲といえば、どうしても《交響曲第6番「悲愴」》や《交響曲第5番》といった後期の作品が注目されがちです。しかし、実はこの第1番こそ、チャイコフスキーの瑞々しい若さとロシアの自然への愛情が素直に表現された貴重な一作であり、冬の季節にぴったりの音楽です。
しかも、冬の情景を描いたクラシック作品は意外と少なく、冬になると聴きたくなるクラシックといえば、《くるみ割り人形》やヴィヴァルディの《四季》の《冬》くらいしか思い浮かばないという方も多いと思います。そうした中で、この《冬の日の幻想》はぜひ知っておきたい隠れた名曲といえます。

各楽章の内容&聴きどころ
それでは、各楽章の内容と聴きどころを紹介します。
第1楽章《冬の旅の幻想》
雪がキラキラ舞うようなヴァイオリンの静かなトレモロ(同じ音を細かく繰り返す演奏方法)の伴奏のうえを、少し冷たい、何か不思議な印象を与えるフルートの旋律で始まります。
雪が降り積もった上をザクザク通るような弦楽器の感じや、風が通り抜けるような管楽器のメロディーを聴いていると、寒い雪の中をソリに乗って駆け抜けているような印象を受けます。
第2楽章《陰気な土地、霧の土地》
チャイコフスキーが訪れたラドガ湖(ロシア西部の湖)の印象をもとに作曲された楽章と言われおり、この曲の最大の聴きどころです。
弦楽器と木管楽器による切ない旋律が、しんしんと雪が降る情景を描きます。チャイコフスキーの作る悲しげなメロディは聴く人の心をひきつけますが、この作品ではちょっと長すぎるかなーと感じる辺り、まだまだ完成されていない印象を受けます。
曲の構成や雰囲気はチャイコフスキーの交響曲第5番2楽章に似ています、聴き比べるとチャイコフスキーの成長を感じられるかも知れません。
第3楽章《スケルツォ》
ワルツ形式の3楽章は、弾むようなリズムと軽やかなフレーズが特徴です。
冬の楽しげな風景も感じさせ、チャイコフスキーらしい躍動感に満ちています。中間部のトリオでは民謡のような雰囲気の優しい旋律が現れ、全体のバランスがとても良い楽章です。
終盤は第4楽章に向けて雰囲気が変わりますが、そこで交響曲では珍しくとても短いですがチェロのソロパートが出てきます。チェロからビオラ、ヴァイオリン、管楽器へとソロでつなぐ場面が登場します。
どちらかというと主題を優雅に弾く事の多いチェロですが、このメロディーは入りが分かりにくく、リズムがややこしい上に、スラーとスタッカートと弾き分けが大事でとにかく厄介な部分です。曲は好きだけど演奏会で弾きたくないなぁと思っていました。
あまり聴くことが無いであろうチェロのソロパート、せっかくなのでお聴きください。
第4楽章《フィナーレ》
ファゴットの低い主題から始まる最終楽章。この主題はロシアの民謡に基づいており、形を替え、楽器を替え、次々と現れます。途中、コサックダンスが目に浮かぶようなメロディーも出てきてとても楽しい楽章で、複数の主題が交錯しながら盛り上がり、短調から長調へ転調、チャイコフスキーらしい明るく派手で壮大なクライマックスを迎えます。
2楽章でも感じましたが、同じことの繰り返しが少し冗長に感じる場合もありますが、まだ若いチャイコフスキーの粗削りな面と、持ち前のメロディの美しさを感じられる楽章となっています。
おすすめ動画紹介
Youtubeのおすすめ動画をご紹介します。
動画は日本人の八嶋恵利奈さん指揮、ドイツのHR交響曲の演奏です。他の動画と比べてテンポがやや速く、チャイコフスキーのイメージを一番表現している演奏だと感じます。各楽器がハッキリ際立つ演奏でとても聴きやすく、この曲を初めて聴く方に向いていると思います。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
チャイコフスキー《交響曲第1番「冬の日の幻想」》は、若き日の詩情とロシアの自然への憧れがぎゅっと詰まった作品です。冬の静かな時間にぴったりで、読書のBGMなどリラックスタイムにおすすめです。特に第2楽章は、心が穏やかに満たされる珠玉の名曲として愛されています。
もしこの曲を気に入ったなら、次はチャイコフスキーの《交響曲第4番》《交響曲第6番 悲愴》、そしてグリーグの《ペール・ギュント組曲》や、シベリウスの《交響曲第2番》も北欧の寒さや自然を感じさせてくれる作品なので、ぜひ聴いてみてほしいです。