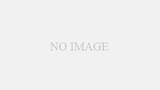この記事でわかること
-
アレクサンドル・ボロディンとこの曲の誕生秘話
-
各楽章の内容と聴きどころ
-
初演当時のエピソードと不評の理由
-
名盤&おすすめの動画
-
この曲が登場した意外なシーン
-
ボロディンにまつわる小ネタ・雑学
ボロディンと《交響曲第2番》誕生の背景
アレクサンドル・ボロディン(1833–1887)は、ロシア民族主義音楽の流れを代表する「ロシア五人組」のひとり。医学・化学者という異色の肩書きを持ちながら、民族色あふれる情熱的な作品を残しました。
《交響曲第2番ロ短調》は、彼の代表作のひとつ。1869年頃に作曲が始まり、完成までなんと7年もかかっています。作曲の途中で仕事や私生活、他の作曲の依頼に追われ、何度も中断。そのうえ、1877年の初演では期待された成果を得られず、不評という苦い経験を味わいます。
リムスキー=コルサコフの助言を受けて改訂を行い、1879年に再演。そこで初めて高い評価を受け、ロシア音楽界にその名を刻むことになります。
この曲は、ボロディン自身が「ロシアの英雄を描いた交響詩的作品」と位置付けており、民謡的要素、正教会の聖歌、東方趣味が色濃く盛り込まれています。
曲の構成と聴きどころ
第1楽章 アレグロ(ロ短調)|英雄の登場と叙事詩の幕開け
冒頭、重厚なホルンとトランペットによるファンファーレが英雄の登場を告げ、壮大な幕開け。荘厳な雰囲気の中にロシアの聖歌風の旋律が響きます。弦楽器が奏でる第2主題は優美で抒情的。展開部では主要主題がドラマティックに展開し、緊張感ある構成に。
一言まとめ:勇ましく、荘厳で英雄叙事詩の開幕を告げる楽章。
聴きどころ
-
重厚なホルンとトランペットのファンファーレ
-
民謡風の甘美な第2主題
-
展開部の対話的なドラマと管弦楽の躍動感
-
ティンパニとホルンのリズム動機
第2楽章 スケルツォ(ヘ長調)|東方趣味と舞踊の愉しさ
複雑な拍子変化と跳ねるようなリズムが印象的。木管群が奏でる軽快な主題と、弦楽器の跳躍が躍動感を生みます。トリオ部分では、クラリネットとオーボエによる中央アジア風の旋律が幻想的。まるでロシアの草原を駆け抜けるかのような一幕。
一言まとめ:民族舞踊のように軽やかで異国情緒あふれる楽章。
聴きどころ
-
複雑な拍子変化とリズムの躍動
-
トリオ部の東方風の旋律
-
再現部の怒涛のテンポアップと迫力
第3楽章 アンダンテ(変ニ長調)|孤高のロマンと叙情詩
一転して静けさと抒情性に満ちた楽章。ホルンによる詩的な旋律から始まり、オーボエ、クラリネット、弦が優しく寄り添うように展開。中間部では金管とティンパニが重厚なコラールを奏で、荘厳な雰囲気を醸します。
一言まとめ:英雄の内面を映し出す、哀愁と郷愁の抒情詩。
聴きどころ
-
ホルン・ソロの抒情的旋律
-
中間部の金管コラールとティンパニ
-
再現部での木管と弦の繊細な掛け合い
第4楽章 フィナーレ(ロ短調)|勝利と凱旋の壮麗な終幕
民族舞曲風の華やかな主題がオーケストラ全体で高らかに奏でられ、勝利の凱旋を描く終章。中盤ではトランペットとトロンボーンのレチタティーヴォが、英雄の栄光を物語るかのよう。祝祭的なクライマックスへと雪崩れ込む。
一言まとめ:圧倒的な熱量と民族色で英雄の凱旋を描く終章。
聴きどころ
-
民族舞曲風の主題とその高揚感
-
レチタティーヴォの劇的効果
-
ティンパニと金管の炸裂するフィナーレ
この曲、実はこんなところでも!
意外にも、この《交響曲第2番》は映画やドラマ、ゲーム音楽の元ネタとしても一部使われることがあります。特に第2楽章や第4楽章の躍動感あるフレーズは、ロシア映画やゲームの戦闘シーンにマッチしやすく、BGMアレンジとしても人気。最近では動画配信サイトでこの曲をBGMに使うクリエイターも増えています。
名盤&おすすめ動画
動画
-
Youtube:ロジェストヴェンスキー指揮/モスクワ放送響(リンク推奨)
名盤
-
エフゲニー・スヴェトラーノフ/ロシア国立響:ロシア情感と重量感の頂点
-
ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー/モスクワ放送響:緊張感と構成美の妙
-
ベルナルト・ハイティンク/ロンドン・フィル:明晰で聴きやすい定番
状況別で
-
初めてなら:ハイティンク盤
-
ロシアの情熱を感じたいなら:スヴェトラーノフ盤
-
繊細さと劇的さなら:ロジェストヴェンスキー盤
まとめ|この曲の魅力と次に聴くべき曲
ボロディン《交響曲第2番ロ短調》は、ロシア民族音楽の精髄を詰め込んだ傑作。英雄叙事詩のような構成と、民謡、正教会聖歌、東方趣味を織り交ぜ、聴く者を異国情緒とドラマティックな世界へと誘います。
次に聴くべきおすすめ曲
-
ボロディン《だったん人の踊り》
-
ムソルグスキー《展覧会の絵》
-
リムスキー=コルサコフ《シェヘラザード》
もっと楽しむ!ボロディン小ネタ集
-
職業は本職の化学者で、作曲は趣味レベルと自称
-
実はオペラ《イーゴリ公》も大傑作(《だったん人の踊り》の原曲)
-
改訂前の第2番初演は、スコアが未完成&オーケストラ練習不足という悲惨な状況だった
-
ボロディンは女性の地位向上にも尽力し、ロシア初の女子医学校設立に関わった