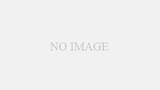今回は、ボロディン作曲の《弦楽四重奏曲第2番》をご紹介します。
「深い愛情」が表れている本作は、クラシック音楽ファンのみならず広く親しまれており、映画やドラマ、結婚式などでも耳にする機会が多い名曲です。
クラシック音楽初心者の方にも分かりやすく、この作品の魅力を解説していきます。
ボロディンとは
アレクサンドル・ボロディン(1833年~1887年)は、ロシア帝国のサンクトペテルブルクで生まれました。幼少期から音楽と科学の才能を併せ持ち、ピアノや作曲を学ぶと同時に化学を専攻し、医師や化学者としても優れた業績を残しました。彼はロシア五人組(バラキレフ、ムソルグスキー、キュイ、リムスキー=コルサコフ、ボロディン)の一員として、民族的な要素を取り入れた音楽作りに貢献します。
本業は化学者で、「ハンスディーカー反応」という有機物の化学反応を発見したことでも有名で、「ボロディン反応」とも呼ばれています。
本業の合間に作曲を行っていたことから、日曜大工ならぬ、「日曜作曲家」と自称していたそうです。それでは次に、作曲当時の背景についてご説明します。
作曲の背景/現代での評価
では、そんな多忙なボロディンはクラシック史上最高とも言える甘い旋律をどのようにして生みだしたのでしょうか。そこにはボロディンの深い「愛」がありました。
妻への愛
ボロディンがこの弦楽四重奏曲を書いたのは1881年の夏。彼は当時、妻エカテリーナ・セルゲーエヴナとのプロポーズ20周年を祝うために、この作品を作曲したと伝えられています。二人は1859年に結婚し、結婚生活の中でボロディンは多忙な化学者・医師・作曲家としての生活を送りながらも、妻への愛情を絶やしませんでした。
この弦楽四重奏曲は、彼の妻エカテリーナへの深い愛情と、二人の思い出を音楽で表現したものとされており、第1楽章冒頭のチェロの旋律は結婚当初の二人の出会い、第4楽章では、楽しいロシア舞曲のリズムが夫婦の幸福な家庭生活を象徴しているとも言われます。
弟子であり親友だった作曲家リムスキー=コルサコフの回想録や、音楽学者の研究からも、この弦楽四重奏曲はボロディンのもっとも私的な作品と見なされており、結婚生活へのオマージュであることが裏付けられています。
現代での評価
弦楽四重奏曲第2番は、全体を通して非常に親しみやすく、のびのびとした旋律が特徴です。特に第3楽章「ノクターン」は、ボロディン自身と妻との愛の象徴とされ、のちにミュージカル《キスメット》(1953)でも「And This Is My Beloved」として引用され、アメリカでも大人気となりました。
また、ディズニーの短編映画作品「マッチ売りの少女」では全編を通じて第3楽章が使われており、人気の高さを物語っています。
それでは、次に各楽章の内容と聴きどころをご紹介します。
各楽章の内容&聴きどころ
この作品は全4楽章から成り立っており、それぞれ異なる表情と物語性を持っています。それでは1つ1つ紹介していきます。
第1楽章:Allegro moderato(ニ長調)
冒頭からチェロと第1ヴァイオリンの掛け合いが印象的で、まるで恋人同士の対話を思わせるような親密さがあります。ニ長調という明るく快活な調性が、幸福感と自然な抒情性をもたらします。
楽章は、伸びやかで歌うような第1主題と、穏やかで優美な第2主題が対比され、展開部では主題が巧みに絡み合いながら発展。再現部を経て、温かなコーダで締めくくられます。
第2楽章:Scherzo. Allegro(ヘ長調)
軽快で躍動感あふれるスケルツォ楽章。細かな音型の動きとリズミカルなアクセントが特徴で、まるでロシアの民俗舞踏のような雰囲気を醸し出します。中間部ではチェロのアルペジオが響き、上に乗るヴァイオリンの甘美な旋律が心地よいコントラストを生みます。
この楽章では、ボロディンが得意とする民族的リズム感が遺憾なく発揮され、《交響曲第2番》や《中央アジアの草原より》を想起させる、聴く者を自然と楽しい気分にさせてくれます。
第3楽章:Notturno. Andante(イ長調)
「ノクターン」と題されたこの楽章は、弦楽四重奏曲第2番の中でも最も有名で、単独で演奏されることも多い名旋律です。冒頭、チェロが豊かな音色で主題を奏で、続いて第1ヴァイオリンが高音で旋律を受け継ぎます。
この甘く叙情的なメロディは、ボロディンの妻エカテリーナへの愛情をそのまま音にしたかのようで、クラシック史上最高と言えるほどの素晴らしいメロディーだと思います。まるで夜の静寂の中、二人だけの語らいが聞こえてくるような美しさです。
演奏したときの私の感覚は、夜の静かな湖のうえを二人の妖精が静かに踊っているようなイメージを持っていました。中間部では、主題が変奏されながら展開し、再び冒頭のメロディが戻ってきて静かに幕を閉じます。
第4楽章:Finale. Andante – Vivace(ニ長調)
終楽章は、序奏部で問いかけるような主題が提示され、それが活気あるヴィヴァーチェの主部へと発展します。リズミカルな動きと軽快な掛け合いが続き、楽章の後半では第1楽章の動機も回帰しながら、全曲をまとめ上げる役割を果たします。ボロディンの構成力とドラマティックな展開の巧みさが際立つ楽章です。
おすすめ動画紹介
では、おすすめの演奏動画をご紹介します。
人気の高い弦楽四重奏曲なので多くの演奏動画がありますが、作曲者の名前を冠したボロディン弦楽四重奏団の演奏をご紹介します。
ロシアの伝統を受け継ぐ彼らの演奏は、作品の本質を捉え、情感豊かでありながらも透明感のある響きが特徴です。クラシック史上最高とも思える甘い旋律をたっぷり演奏してくれる演奏をチョイスしました。聴く人によって好みは変わって来ますが、他にもエマーソン弦楽四重奏団やジュリアード弦楽四重奏団の録音も高く評価されています。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
アレクサンドル・ボロディンの「弦楽四重奏曲第2番」は、愛と自然、ロシアの情緒が凝縮された珠玉の室内楽作品です。とりわけ第3楽章「ノクターン」は、優美で甘美な旋律が心を打つ名曲であり、クラシック音楽初心者にもぜひ触れていただきたい一曲です。